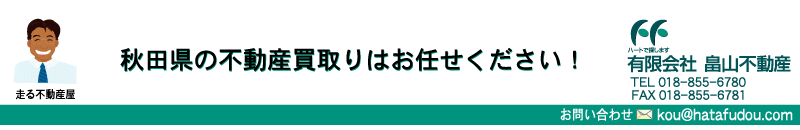|
昨日秋田駅前の東洋の食堂?とかいうハイカラな店で、にんにくのから揚げをたべました。今朝なまはげはじめ、娘三人から出て行けと言われてしまいました。寝室他、家中が臭かったようです。普段からくさいのに考えられないとのことでした。みんなお父さんのことが大好きなんですね。
さて今日は今週の倫理460号を掲載します。
再現した町づくりで観光客を集めることに成功した地域です。レトロな雰囲気が色濃く感じられる商店街に、多い日には一日五十台もの観光バスが訪れます。
もともと豊後高田は、江戸時代から国東半大分県豊後高田市は、昭和の町並みを島一の賑やかな町として栄えていたのですが、昭和三十年代初めに約三万人で人口のピークを迎えた後は減少傾向が続き、約一八〇〇〇人にまで減りました。
市内には、かつて町に活気があったときに形成された六つの商店街がありましたが、人口の減少に加えて郊外大型店の出店などもあり、衰退の一途を辿っていました。
そうした状況を何とか打開しようと、豊後高田市の商店街再生に向けた取り組みが、一九九二年から市職員や地元商店街の有志の方々を中心にスタートしたのです。人々は自主的な勉強会を開催し、また、イベントを実施する等の試行錯誤を続ける中で、「レトロ」あるいは「昭和」というコンセプトを徐々に醸成していったのです。
二〇〇〇年には「商店街まちなみ実態調査」を実施。商店街を構成する約三百軒の商店を詳細に調べ、商売の内容、扱っている商品の内容はもとより、商店主のプロフィールや建物の建築年までを網羅した調査を行ないました。
その結果判明したのは、商店主の「高齢化」が進んでいるということと、建物の「老朽化」が進んでいるということでした。しかし豊後高田の人たちは、そうしたネガティブに思いがちなものを、ポジティブな要因として捉えたのです。
商店主が高齢であるということは、町が栄華を誇った昭和三十年代当時から商売の一線に立ち続けてきたということであり、建物の老朽化は、それだけ古い建物が多いということ。つまり、商店主(ソフト)にも建物 (ハード)にも「昭和」を再現するリアリティさがあるということを意味します。商店街は町がもっとも輝いていた「昭和三十年代」を、再生の中心テーマに据えました。
翌二〇〇一年には、様々な商店の看板や店の外装を昭和風へと改装。費用の一部を県・市が補助するなどの支援事業もスタートしました。また、古い商売道具を「お宝」として展示する「一店一宝」運動、昭和らしい特徴のある商品を売る「一店一品」運動なども展開し、昭和の商店街を甦らせました。
こうした取り組みが功を奏し、観光客数はスタート時の二〇〇一年度に約二万五〇〇〇人を集め、四年後の二〇〇四年度には初年度の十倍近い約二五万人を集めるに至ったのです。
「弱みを強みに転じる」という見方があります。豊後高田市の「昭和の町」は、高齢化や老朽化という、ともすると弱みとも受けとめられがちな「過去」を強みに変えてしまいました。思考の柔軟性は、事業商売の要です。打つ手を求める中に、光は射し込むのです。
|