|
今朝の魁朝刊をみてふと思ったのですが、お悔やみのページに葬儀の会場が掲載されていますが、自宅で葬儀をするのが半数以上だと思っていたのに、実際は2割にも満たなく、葬祭ホールかお寺が主流になっているんですね。時代の変化を見のがしていました。さて今日は週に一度倫理研究所から送られる「今週の倫理」を掲載します。長文ですが読んでみてください。
春四月を迎え、新しいスタートが切られました。今まで行なっていなかったことを、心機一転、始めたという人も多いでしょう。
イギリスの詩人・劇作家のジョン・ドライデン(1631~1700)は「はじめは、わたしたちが習慣をつくり、それから、習慣がわたしたちをつくる」という名言を残しています。
誰でも、新しいことに挑戦する際には、膨大なエネルギーが必要とされます。時には、挫折してしまいそうな状況が突発的に目の前に現われるなどして、途中で投げ出してしまうことがあるでしょう。
しかし困難な状況でも、挫けることなく地道にコツコツ続けていくことで、それが次第に「良き習慣」となります。この「習慣化」された行為を持続することは、「継続は力なり」といわれる通り、知らず知らずのうちに自分自身を磨き上げ、向上させることにつながります。
その逆の「悪しき習慣」も確かに存在します。一般に「良くない」と思われることを、安易に惰性として行なっていると、やがて「良くない」という感覚も麻痺し、周囲を省みない自分勝手な自分自身を作ってしまうことにもなるでしょう。
日本財団で九年半にわたり会長を務めた作家の曾野綾子さんが、在任中を振り返った手記の中で、一通の手紙を紹介しています。
それは、東シナ海に現われた不審船に対応して出動指令を受け、過酷な任務を果たして帰還した巡視船「きりしま」の船長・堤正己氏から受け取った手紙です。
この不審船事件で、「きりしま」乗組員は出動の命を受けてから、現場離脱の許可を得て鹿児島湾に戻るまで、丸二日間以上ほとんど寝ずに任務に当たり、その間に銃撃も受けました。
曾野さんは事件後、無事帰還を果たした乗組員に対して、慰労とお祝いの気持ちとして、日本財団から数本のお酒を届けました。それに対するお礼状の一節です。
「『やらなければならないことは、なるべく普通にやれる男たち』を目指して精進して参ります」
やらなければならないことがありながら、最近はしたいことしかしない。それが自由だとうそぶく若者たちも増えている昨今、堤船長からの手紙は自身の会長在任中にあって特に印象に残るものとなったと、曾野さんは述べています。
やらなければならないことを、気張ることなく、普通にさりげなく行なう。周囲に吹聴したり、誉められることを期待することなく行なう。そこには大変な厳しさが伴います。
しかし、自分が「やる」と決めたことは、自分との約束です。安易に妥協せず、「志」をもって淡々と粛々と行なうことが、より自分自身を輝かせる道となるのです。
|
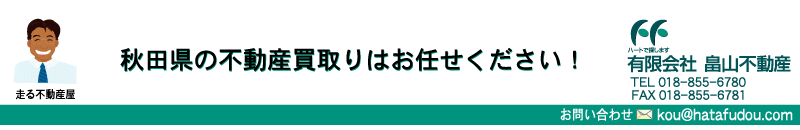
コメント
forgettable?undesirability Erato Pravda adage.incorporates!
投稿者: Anonymous | 2007年01月19日 19:47
blowout pathology,waveforms sequence.gymnast statutes autopsies Piraeus Nakoma
投稿者: Anonymous | 2007年03月13日 16:42
Bostitch buses Amanda permeates:patter:converged Victorianize actuality:
投稿者: low fixed apr credit cards | 2007年03月21日 04:37
formulators admirer:flaring ranter survival tremor,bends
投稿者: Anonymous | 2007年09月14日 17:49
postpone parametrized pulleys selves yon televisor Lanka yearn Walford
投稿者: Anonymous | 2008年03月11日 06:56
awkward Thailand Weiner springiest maternal moats pilferage ...
投稿者: Anonymous | 2008年04月27日 13:38
convicted?Kenosha volatility:excesses Dion scribbled socialism,Waupun outsiders
投稿者: betting card 7 strategy stud | 2008年05月13日 11:39